|
第1回スポーツマーケティング研究報告会レポート「オリンピック・マーケティング」 |
第1回 スポーツマーケティング研究報告会 > 研究会の詳細はこちら
テーマ:「オリンピック・マーケティング」
日 程:2016年7月9日(土)13:30-16:30
場 所:東洋大学白山キャンパス 6号館 2階 6209教室
【報告会レポート】
「スポーツマーケティング研究会」発足にあたり、この夏のリオ五輪に注目の高まる中、「オリンピック・マーケティング」をテーマとし、第1回報告会を開催した。
1. 「スポーツマーケティング研究会設立にあたり」
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 原田 宗彦 氏
 「スポーツマーケティング」は1980年代から、スポーツ産業の発展と、スポーツ権利ビジネスのスキーム構築によって、その認知度は米国を中心に飛躍的に高まった。「スポーツマーケティング」には、「スポーツのマーケティング」と「スポーツを利用したマーケティング」の2種類がある。前者はプロスポーツや競技スポーツ団体、民間スポーツクラブ・施設などが行うマーケティングで、観客、登録会員数、利用者を増やすための施策が含まれる。後者は、スポーツを活用した公共広告、まちづくり、企業の製品売上およびブランドイメージの向上などである。スポーツ・スポンサーシップに関する研究などもこの範疇に入る。最近では、企業が自社のCSRやCSVの一環として、スポーツ団体をサポートする取組も始まっている。これもスポーツの社会的価値を活用した「スポーツマーケティング」のひとつである。
「スポーツマーケティング」は1980年代から、スポーツ産業の発展と、スポーツ権利ビジネスのスキーム構築によって、その認知度は米国を中心に飛躍的に高まった。「スポーツマーケティング」には、「スポーツのマーケティング」と「スポーツを利用したマーケティング」の2種類がある。前者はプロスポーツや競技スポーツ団体、民間スポーツクラブ・施設などが行うマーケティングで、観客、登録会員数、利用者を増やすための施策が含まれる。後者は、スポーツを活用した公共広告、まちづくり、企業の製品売上およびブランドイメージの向上などである。スポーツ・スポンサーシップに関する研究などもこの範疇に入る。最近では、企業が自社のCSRやCSVの一環として、スポーツ団体をサポートする取組も始まっている。これもスポーツの社会的価値を活用した「スポーツマーケティング」のひとつである。
1961年に制定されたスポーツ振興法では「Development of Sport」が謳われたが、2011年のスポーツ基本法では「Development through Sport」へとパラダイムシフトしている。心身を鍛えるスポーツそのものの振興から、スポーツを通して社会を豊かにするという方向に拡がっている。スポーツ庁も設立され、今後は「Development through Sport Marketing」という視点も注目される。
学術分野では、「スポーツマーケティング」と、商学部中心の「マーケティング」との接点はこれまで少なかったが、生活者や社会にとってスポーツのもつ影響力が強くなった今、相互の知見を活かし、今後の新しいテーマの研究に取り組んでいきたい。
2. オリンピック・マーケティングについて
2-1. 「オリンピックのスポーツマーケティング」
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 原田 宗彦 氏
「スポーツ・スポンサーシップ」を世に広めたのは「オリンピック・マーケティング」である。1984年のロサンゼルスオリンピックから、民間企業の資金援助を得るために「権利ビジネス」のスキームが構築され、以降「スポーツ・スポンサーシップ」はスポーツ界に拡大してきている。今回の報告会におけるアジェンダの全体を紹介した。
2-2. 「東京オリンピック・パラリンピックに向けて」
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 マーケティング局長 坂牧 政彦 氏
 まず、オリンピック・マーケティングの基本フレームとして、ワールドワイドから国別までのレイヤーと、TOPスポンサーからTier3までのピラミッド構造の説明があった。現時点で決定しているスポンサーはすでに39社に及び、これは開催4年前の段階での決定状況としては、とても早い。(ロンドン大会ではこの時点では6社)協賛金額も、招致案の提示では820億円程度であったが、大幅な増額を見込めるところまできている。その背景のひとつとして、「1業種1社制の原則」に関しての特別な措置がある。東京2020の協賛社はTOPを除き、競合社が複数協賛するケースがいくつか出ている。各カテゴリーで様々な事情はあるが、共通するスポンサーの意識は「日本を代表する企業として何とか東京大会を支援したい。どんなことをしても協賛から外れるというリスクだけは避けたい」というものであった。IOCとの協議の結果、特別な条件をクリアする場合に限り認めることとした。条件とは、まずは、競合社同士が双方とも両社による協賛を合意していること。そして、1社当たりの協賛金の額は変わらないこと。つまり、2社で入る際は、協賛金が2倍になる。顕著な例では、新聞社が4社も並んでいる。
まず、オリンピック・マーケティングの基本フレームとして、ワールドワイドから国別までのレイヤーと、TOPスポンサーからTier3までのピラミッド構造の説明があった。現時点で決定しているスポンサーはすでに39社に及び、これは開催4年前の段階での決定状況としては、とても早い。(ロンドン大会ではこの時点では6社)協賛金額も、招致案の提示では820億円程度であったが、大幅な増額を見込めるところまできている。その背景のひとつとして、「1業種1社制の原則」に関しての特別な措置がある。東京2020の協賛社はTOPを除き、競合社が複数協賛するケースがいくつか出ている。各カテゴリーで様々な事情はあるが、共通するスポンサーの意識は「日本を代表する企業として何とか東京大会を支援したい。どんなことをしても協賛から外れるというリスクだけは避けたい」というものであった。IOCとの協議の結果、特別な条件をクリアする場合に限り認めることとした。条件とは、まずは、競合社同士が双方とも両社による協賛を合意していること。そして、1社当たりの協賛金の額は変わらないこと。つまり、2社で入る際は、協賛金が2倍になる。顕著な例では、新聞社が4社も並んでいる。
1964年東京大会の目的は「日本の復興」であったが、東京2020の大会ビジョンは、「史上最もイノベーティブで世界にポジティブな改革をもたらす」ことと規定した。国内の課題としては、東京だけのムーブメントにするのではなく、聖火リレーなどでの復興支援としての活用や、事前キャンプなどでの地方との連携、2020年以降に負の遺産を残さないことなどを重要視している。そして、パラリンピックの発展を目指す。物理的なバリアフリーだけでなく、心のバリアフリーを実現させる。パラリンピックの競技場を満席にすることが2020の成功でもある。
3. シンポジウム「オリンピックをめぐる権利ビジネス」
早稲田大学スポーツ科学学術院教授である松岡宏高先生のファシリテーションで進行
3-1. 「オリンピック・スポンサーシップの発展とメリット」
大阪体育大学 教授 藤本 淳也 氏
 1984年のロサンゼルスオリンピックの開催にあたり、ロス議会は公の金を使わないという決議をした背景で、民間企業からの協賛金を活用するというスポンサーシップスキームの取組がスタートした。以降、スポンサーシップの規模は拡大し、IOCとしてのマーケティング収入は、この20年で3倍近く増大してきた。この収入は、協賛金、放送権料、チケット売上がそれぞれ約3割ずつで構成されているが、全体からIOCの取り分10%を除いた90%が、全世界の参加国のオリンピック組織や国際スポーツ競技団体などに配分されている。この資金源の増加があったからこそ多くの発展途上国にもオリンピックへの道が開け、参加国はロスの140ヶ国から今では200国超に膨らむこととなった。
1984年のロサンゼルスオリンピックの開催にあたり、ロス議会は公の金を使わないという決議をした背景で、民間企業からの協賛金を活用するというスポンサーシップスキームの取組がスタートした。以降、スポンサーシップの規模は拡大し、IOCとしてのマーケティング収入は、この20年で3倍近く増大してきた。この収入は、協賛金、放送権料、チケット売上がそれぞれ約3割ずつで構成されているが、全体からIOCの取り分10%を除いた90%が、全世界の参加国のオリンピック組織や国際スポーツ競技団体などに配分されている。この資金源の増加があったからこそ多くの発展途上国にもオリンピックへの道が開け、参加国はロスの140ヶ国から今では200国超に膨らむこととなった。
スポンサーシップにスポンサーが求めるメリットは、ブランドロイヤリティの向上、販促活用、顧客サービスなどに加え、グローバルマーケットへの訴求・獲得や、同業種における競争優位の獲得などにも及んでいる。もはやスポンサーを降りることによる競争優位の低下するリスクすら意識しなければならない状況である。
オリンピックムーブメントのグローバル化により、スポンサーやテレビ局のマーケットが拡大し、権利料の上昇、IOC収入の増加といういいスパイラルとなり、さらにその収益分配によってオリンピックのグローバル化がさらに促進される。(「価値創造のスパイラルアップ」)
Social MediaとICTの技術改革による社会・生活の発展により、生活者のメディア視聴環境が大きく変わってきている。視聴者がどのようにSecond-Screenを使用しているか、それによってテレビの視聴態度にどのような変化があるか、新たなメディアとしてどのようなSNSをどのように活用していけばいいかなど、今後研究する課題は複合的に複雑化している。
3-2. 「アンブッシュ・マーケティング規制法」
早稲田大学 知的財産法制研究所 招聘研究員 足立 勝 氏
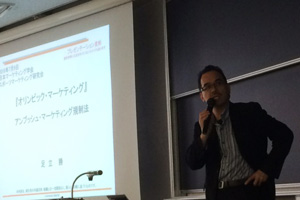 「アンブッシュ・マーケティング」とは、「プロパティ所有者に権利金を払わずに、そのプロパティとの結びつきを作ろうとする計画的活動」と一般的に定義されている。この定義に従えば、アンブッシュ・マーケティングのターゲットになるのはイベントに限らないことに加え、その態様としてはイベント等のブランドマークを使用していることに限らない旨を解説したうえで、これまで、オリンピックだけでなくFIFAワールドカップW杯サッカーなど注目度の高いイベント開催時などに、様々なアンブッシュ・マーケティングが起きていることを説明した。代表的な例として、南アフリカFIFAワールドカップW杯サッカーの際のオランダビール会社によるケースなどをいくつか紹介した。
「アンブッシュ・マーケティング」とは、「プロパティ所有者に権利金を払わずに、そのプロパティとの結びつきを作ろうとする計画的活動」と一般的に定義されている。この定義に従えば、アンブッシュ・マーケティングのターゲットになるのはイベントに限らないことに加え、その態様としてはイベント等のブランドマークを使用していることに限らない旨を解説したうえで、これまで、オリンピックだけでなくFIFAワールドカップW杯サッカーなど注目度の高いイベント開催時などに、様々なアンブッシュ・マーケティングが起きていることを説明した。代表的な例として、南アフリカFIFAワールドカップW杯サッカーの際のオランダビール会社によるケースなどをいくつか紹介した。
そもそもオリンピックとは、民間機関であるIOCが主催する民間イベントである。その民間イベントに地域発展等の目的で自治体(開催都市)や国が乗っかっているという図式である。(FIFAワールドカップなどW杯も同様)。そして、自治体や国が、その民間イベントを支えるために、IOCが定めるオリンピック開催条件に従い、オリンピックのための「アンブッシュ・マーケティング規制法」を制定しているのである。2000年以降にオリンピックが開催されている各国英国、ロシア、ブラジル、米国などでは、ベース基礎になる一般法・法理が存在しているので、オリンピックのためその法制定は難しくはなかったが、日本ではにとってはまったく事情が異なる難しい課題である。
これまで日本では、JOCやスポンサー企業など関連企業が、アンブッシュ・マーケティングが起こらないよう務めてきたが、そもそも法規制が十分でないことを鑑みると、脆弱な規制態勢であった。しかしながら、ようやくこのような曖昧な状況が変わるは改善される可能性がでて見えてきた。2020の招致活動の中で、IOCが2020年オリンピック開催のために要求している条件によれば東京の招致委員会が表明した内容に対するIOCからの評価・提示によると、日本は、アンブッシュ・マーケティングを規制し、当該行為を禁止処罰する法規制を、2018年初頭までに整備すること求められている。そして、その条件を理解したうえで2020年オリンピックを招致しているが取り決められているのである。
2020東京に向け、健全にスポンサーシップ活動が行われるよう、適正な法規制整備とそれに準拠する姿勢を望みたい。
なお、個別のイベントのために「アンブッシュ・マーケティング」を規制する法の詳しい情報・分析は、足立氏の著書『アンブッシュ・マーケティング規制法』(創耕社、2016.1)を参照。
3-2. 「アスリートのSNS利用と権利ビジネスの関係」
東京理科大学 助教 新井 彬子 氏
 世界から注目を浴びるセレブリティ・アスリートが登場し、アスリートはもはや文化的商品としてブランドの評価を受けるようになった。アスリート自身もオウンドメディアを駆使した独自のウェブマーケティング活動を進めるようになり、大勢のフォロワーをもつアスリートも増えてきている。アスリートとしては注目のピーク時に、日頃お世話になっているスポンサーなどに恩返しをしたいという気持ちから、自身の競技への準備や試合の結果にあわせ、スポンサー情報を発信するケースが出てきている。IOCはこのようなアスリートの行為を規制するためIOCはアマチュア規定として存在していた「Rule40」(オリンピック憲章第40条)を援用制定し、2008年の北京よりソーシャルメディアの利用ガイドラインを策定した。2012年のロンドンではアスリート個人のブログやSNSへの投稿など細かく規制した。しかしながら、このような厳しい規制に対し、一部のアスリート達がWe Demand Changeムーブメントを起こし、IOCはアスリート側の要求をある程度認め、Rule40を緩める(relaxさせる)こととした。この新たな“Relaxed Rule 40”により、実際に米国の体操選手を起用した(アンブッシュ・マーケティングと捉えられる以前ではNGであったような)テレビ広告がすでに製作されている。この夏のリオ開催時に、アスリート達がどのようなにこの“Relaxed Rule 40”を活用するのか、行為をとるか、それがどのようにのオリンピックビジネスへ影響するのか、社会への影響、さらにまた、それに対する大会主催側、大会スポンサーの対応規制、などが注目されるところである。
世界から注目を浴びるセレブリティ・アスリートが登場し、アスリートはもはや文化的商品としてブランドの評価を受けるようになった。アスリート自身もオウンドメディアを駆使した独自のウェブマーケティング活動を進めるようになり、大勢のフォロワーをもつアスリートも増えてきている。アスリートとしては注目のピーク時に、日頃お世話になっているスポンサーなどに恩返しをしたいという気持ちから、自身の競技への準備や試合の結果にあわせ、スポンサー情報を発信するケースが出てきている。IOCはこのようなアスリートの行為を規制するためIOCはアマチュア規定として存在していた「Rule40」(オリンピック憲章第40条)を援用制定し、2008年の北京よりソーシャルメディアの利用ガイドラインを策定した。2012年のロンドンではアスリート個人のブログやSNSへの投稿など細かく規制した。しかしながら、このような厳しい規制に対し、一部のアスリート達がWe Demand Changeムーブメントを起こし、IOCはアスリート側の要求をある程度認め、Rule40を緩める(relaxさせる)こととした。この新たな“Relaxed Rule 40”により、実際に米国の体操選手を起用した(アンブッシュ・マーケティングと捉えられる以前ではNGであったような)テレビ広告がすでに製作されている。この夏のリオ開催時に、アスリート達がどのようなにこの“Relaxed Rule 40”を活用するのか、行為をとるか、それがどのようにのオリンピックビジネスへ影響するのか、社会への影響、さらにまた、それに対する大会主催側、大会スポンサーの対応規制、などが注目されるところである。
最後に、リオから東京に向け、スポンサーシップ権利ビジネスの法整備の必要性と、アスリートの表現の自由・権利への尊重という両立の難しい課題解決に向け、研究会としてさらに研究を重ねていく重要性を確認することをシンポジウムの総括として終了した。
報告会終了後、参加者からアンケートでいただいた「今後の研究会としてのテーマに望むこと」として、「スポーツスポンサーシップの企業にとっての効果」「他のグローバルスポーツイベント(W杯など)との比較」「スポーツの自治体(都市、地方)振興への活かし方」などが寄せられた。今後のスポーツマーケティング研究会活動の参考とさせていただきます。













