|
第204回マーケティングサロンレポート「学校のブランディング 〜 ブランディングによる経営改革 ~ 愛知東邦大学を事例に」 |
第204回マーケティングサロン:東京
テーマ:学校のブランディング 〜 ブランディングによる経営改革 ~ 愛知東邦大学を事例に
日 程:2025年2月28日(金)19:00-21:00
場 所:一橋大学 千代田キャンパス 学術センター内 4階 第7会議室
ゲスト:愛知東邦大学 経営学部 教授/学長補佐 上條 憲二 氏
愛知東邦大学 入試広報課 課長 三輪 哲也 氏
サロン委員:今井 紀夫、嶋尾 かの子、深澤 了
【ゲストプロフィール】
 上條 憲二(かみじょう けんじ)氏
上條 憲二(かみじょう けんじ)氏
長野県松本市生まれ。早稲田大学一文学部社会学専攻課程卒業後、1976年、第一広告社(現I&SBBDO)入社。以来、マーケティングプランナー、SPプランナー、アカウントエグゼクティブ、として様々な企業の広告コミュニケーション戦略の立案、ディレクションを行う。広告主は、航空会社、日本車、輸入車、トイレタリー、人材派遣会社、製薬会社、百貨店、ファーストフードなど多岐に亘る。後に、同社の執行役員として、営業全般の統括的な役割および同社のマーケティング部門の責任者を兼任。
2004年から10年間はインターブランドでエグゼクティブディレクターとして企業のブランド戦略を推進。住宅、住宅機器、航空、輸入車、国産車、旅行、ケーブルテレビ、テレビ局、鉄道、高速道路、大学、建設、玩具、医療、スポーツ用品など。現在は、愛知東邦大学経営学部教授。専門は、ブランド構築論、広告・メディア論。
<著作>
『超実践!ブランドマネジメント入門』(単著)2022.2 ディスカヴァー・トゥエンティワン
『ブランディング 7つの原則』(共著)2012.7 日本経済出版社
『21世紀のマスコミリーズ 広告』(共著)1997.9 大月書店
『ブランディング・ドキュメンタリー ブランディングによる経営改革挑戦
-ある地方の小規模な私立大学の改革物語-』2023.11前編・2024.1後編 Amazon Kindle
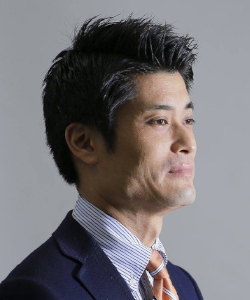 三輪 哲也(みわ てつや)氏
三輪 哲也(みわ てつや)氏
2000年 商社に入社。トヨタ系を中心とした自動車関連企業へBtoBの営業を行う。2013年 学校法人東邦学園 愛知東邦大学入職。総務課を経験したのち、2016年に入試広報課へ配属。学生募集を中心とした広報を行う。同年、ブランド推進委員会が発足。構成員として愛知東邦大学のブランディングに従事。2018年より現職。2021年より日本ブランド経営学会理事。クレド「三方よし」。売り手よし、買い手よし、世間よしの言葉の意味通り、自分だけでなく、自分に関わる人、そして社会に貢献していくことを信条としている。「らしさ」を活かせる人、「らしさ」をめざせる組織、「らしさ」あふれる社会にしていきたい。
【サロンレポート】
人口減少が予想を超えて進み、大学進学率は上がり、もう何年も前から大学は生き残りをかけた戦いが続いています。地方大学は特に苦戦を強いられている中、愛知東邦大学は教員、職員が一体となってブランディングを推進。それは教職員の意識や行動を変え、やがてその影響は学生にも波及していきました。その過程で具体的にどのような取り組みを行ったのか、現場でのリアル話が展開されました。
もともとインターブランドのエグゼクティブ・ディレクターでもあった上條氏は、数々の企業を担当してきた経験から「学園としての歴史が100年ある。だけど知名度がない。それはブランディングでなんとなるかもしれない」と考えます。まずは上條ゼミの学生たちと一緒に勝手にブランディング活動を始めます。学生たちにアンケート調査を行い「学生生活は満足も不満足でもないけど、人には勧めない」という結果を得ます。まずはパンフレットやWebサイトの「見た目」を変える提案を学園側には行い、機運を育てていきました。
上條氏が教員になってから1年後、理事長にブランド戦略を提案。「鉄道の時代の人材を育てた下出民義、リニアの時代の人財を育てる愛知東邦大学」をテーマに、独自にSOWT分析を行い、2015年から2027年までの大学のロードマップを勝手に作成。その提案は理事長の心を打ち、すぐに理事会に諮られ、愛知東邦大学のブランディングが全学的にいよいよ始まります。
 上條氏が中心になって、著書である『ブランディング 7つの原則』(2012.7 日本経済出版社)にもあるブランディングのフレームワークに則り活動が始まります。ブランド推進委員会が教職員で組織化され、分析から行いました。学生への調査でわかったのは、53.7%が非満足層(満足度がどちらでもない+あまり満足していない+全く満足していない)。だということ。その調査結果に基づいて、全教職員対象の座談会を開催します。すべての意見をホワイトボードに書き出し、問題意識を共有。将来へのビジョン、地域密着とは、本学ならではの教育など多くの意見を報告書にまとめ、全員に共有をしました。さらにその座談会をもとにSWOT分析を委員会で行い、コンセプトの軸を考え、スローガンまで考えていきます。そこで決まったのが「オンリーワンを、一人に、ひとつ」。さらに座談会で出た意見を参考に、学生へのクレド、地域へのクレド、仲間へのクレドも整備していきました。
上條氏が中心になって、著書である『ブランディング 7つの原則』(2012.7 日本経済出版社)にもあるブランディングのフレームワークに則り活動が始まります。ブランド推進委員会が教職員で組織化され、分析から行いました。学生への調査でわかったのは、53.7%が非満足層(満足度がどちらでもない+あまり満足していない+全く満足していない)。だということ。その調査結果に基づいて、全教職員対象の座談会を開催します。すべての意見をホワイトボードに書き出し、問題意識を共有。将来へのビジョン、地域密着とは、本学ならではの教育など多くの意見を報告書にまとめ、全員に共有をしました。さらにその座談会をもとにSWOT分析を委員会で行い、コンセプトの軸を考え、スローガンまで考えていきます。そこで決まったのが「オンリーワンを、一人に、ひとつ」。さらに座談会で出た意見を参考に、学生へのクレド、地域へのクレド、仲間へのクレドも整備していきました。
打ち出すイメージも整備します。日本カラーデザイン研究所の「イメージスケール」を参考に、現在の姿を位置づけ、それをどうあるべき姿へ持っていくか。どんなイメージにしたいかを決めていきました。これを土台にVIを変更。ガイドラインを定め、ウェブサイトや大学案内などもそこに基づいて整備していきます。
「見た目」だけを整えるのではなく、教職員全員がマイクレドを決め、学内外で広く公表。高校生を対象にした「じぶんブランディング」講座を展開。自分の言葉で大学4年間をどう過ごすかをアピールする自己プロデュース入試を開始。「オンリーワンを、一人に、ひとつ」を軸に次々に改革を実施します。やがて学生がビジネスについて考えるマイナビ「キャリアインカレ」では学生が決勝大会に進出。インターブランドが主催するJapan Branding Award2019を受賞します。
これらのブランディングを推し進めたブランド推進委員会のメンバーの1人でもあったのが今回のもう一人のゲスト三輪氏。先に書いた「じぶんブランディング」を強力に推し進めてきました。
 「オンリーワンを、一人に、ひとつ」を軸にしたときに、入試広報課として何ができるのか。これまで入試広報として愛知東邦大学が大切にしてきたのは「進学の意義の大切さ」。これらを組み合わせて考え、入試広報課の仕事を「人生の岐路に向き合う仕事」と再定義。広報を高校生への教育と捉え直し、「じぶんブランディング」という高校生向けのキャリアプログラムをオリジナルでつくりだしたのです。テキストも独自で開発し、無償で高校に提供。これまでの受講者は約7000名にまで増えています。
「オンリーワンを、一人に、ひとつ」を軸にしたときに、入試広報課として何ができるのか。これまで入試広報として愛知東邦大学が大切にしてきたのは「進学の意義の大切さ」。これらを組み合わせて考え、入試広報課の仕事を「人生の岐路に向き合う仕事」と再定義。広報を高校生への教育と捉え直し、「じぶんブランディング」という高校生向けのキャリアプログラムをオリジナルでつくりだしたのです。テキストも独自で開発し、無償で高校に提供。これまでの受講者は約7000名にまで増えています。
 高校の探求の授業で行われていくことも多く、これまで高校の先生とは学生募集についての会話だけだったのが、教育というテーマにまで深堀りされることが増えていきます。プログラムは徐々に発展し、高校1年生、高校2年生には「じぶんブランディング・ハイスクール」、高校3年生から大学1年生には「じぶんブランディング・スタートアップ」、大学3年生からは「じぶんブランディング・キャリア」と広がりを見せています。高校3年生から対象になる「じぶんブランディング・スタートアップ」は入学前教育の始まりと位置づけ、入学後は学生が自分のクレドを作成するプログラムになっています。
高校の探求の授業で行われていくことも多く、これまで高校の先生とは学生募集についての会話だけだったのが、教育というテーマにまで深堀りされることが増えていきます。プログラムは徐々に発展し、高校1年生、高校2年生には「じぶんブランディング・ハイスクール」、高校3年生から大学1年生には「じぶんブランディング・スタートアップ」、大学3年生からは「じぶんブランディング・キャリア」と広がりを見せています。高校3年生から対象になる「じぶんブランディング・スタートアップ」は入学前教育の始まりと位置づけ、入学後は学生が自分のクレドを作成するプログラムになっています。
ウェブサイトでは学生を取材し、「TOHO Stories」として紹介。驚くことに学生は取材をほとんど断らず「これに取材されるために頑張っていました!」と言われることも多くなっていきます。学内のサイネージでも紹介し、学生のモチベーションや自己肯定感の向上、就職活動での活用などに寄与しています。
さらに入試広報課では「Good-Will-Canシート」を開発します。高校生がオープンキャンパス中に自分の進路を考えられるように作成。オープンキャンパスの実行委員の学生とベネッセグループでさらにブラッシュアップを行ってきました。
さまざまな展開、推進を行ってきた三輪氏ですが、異動のある組織の中では「意志や想いの伝承」が一番大変であると言います。しかし入試広報とは「人生の岐路に向き合う仕事」という想いを共有することで、こちらの期待以上の動きをすることが多々あり、チームとしてスムーズに動くことができたそうです。
三輪氏は「『オンリーワンを、一人に、ひとつ』は学生、高校生のためのものではなく、教職員、部署のメンバーのためでもある」と話をまとめます。いかに一人ひとりが主体的になれるのか。それを達成するために、学内外でブランド体験を重ねていきたいとむすびました。
あっという間の90分間。その後は上條氏、三輪氏の発表をもとにした質問が出されました。両名から具体的な事例を用いての回答があり、活発なディスカッションが行われました。
【サロンを終えて】
ブランディングは多くの人や企業ごとに解釈が異なる言葉だと感じています。とかく企業の「言葉や見た目」だけをそろえることがブランディングと思われがちな傾向があると感じています。しかし今回のサロンに参加すると、それはあくまでブランディングを構成する一要素で、経営や現場が連動して一気に変わっていく躍動感を感じることができました。アーカーが「いかにブランドを演じる人を社内に増やせるか」と指摘しているように、ブランディングの本質、あるべき姿がここにあり、ブランディング自体が経営そのものになっていると思いました。

(文責:深澤 了)












