|
第26回マーケティングサロンレポート 「コ・クリエーション型マーケティングへの挑戦」 |
第26回 マーケティングサロン
「コ・クリエーション型マーケティングへの挑戦」
日程:2015年2月26日(木)19:00~21:00
場所:日本マーケティング協会 東京本部
ゲスト:
株式会社電通 マーケティングソリューション局 プロデューサー 河野 紳一 氏、チーフアナリスト 濱口 洋史 氏
株式会社電通国際情報サービス 金山 信男 氏
サロン委員:高村和久、三谷暢宣
【サロンレポート】
テクノロジーの進歩などにより、企業から寄せられる課題を解決するための手段としてコ・クリエーションが広く使われるようになり、新商品開発以外のプロモーション領域などでもその活用は拡がりを見せています。
そこで、現在マーケティングの現場で起こっていることを、株式会社電通の現場担当の方より、利用されているテクノロジーと共に、事例をベースとしながらご紹介させていただきます。
また、こういった現状をふまえ、株式会社電通が新たに挑戦しているサービスをご紹介していただきながら、今後どのような可能性と課題がコ・クリエーション型マーケティングにありそうか、お話していただきました。
【概要】
「既存のマーケティングがなかなかうまくいかない」「革新的なサービス・商品を作りたい」という要望に応え、ユーザーのみならず様々なステークホルダーが参加する「コ・クリエーション」を進める電通 マーケティングソリューション局。
「守秘義務がある仕事についてはお話できないので、良く知られている例を」ということでしたが、随所に現場ならではのコメントが伺え、非常に興味深いお話を伺うことができました。
■コ・クリエーションとはなにか
初めに、いま世の中にある様々な「コ・クリエーション」の事例をご紹介頂きました。
新商品・サービス開発の事例として
・トリンプインターナショナルの「究極のランジェリー」
・良品計画の「くらしの良品計画所 IDEA PARK」
・UNIQLOと小学館のコラボレーションによる新商品開発
・グリコと「Mart」のコラボレーションによる「マート読者とつくったポッキー」
・「ダイアログ・イン・ザ・ダーク・タオル」
マーケティング分野では
・雪印メグミルクの「俺たちの“ゆきこたん”プロジェクト」
・共創プラットフォーム「eYeka」
インナーアクティベーションの事例では
・Panasonicの「One Panasonic」
流通チャネル開発では
・ネスカフェ アンバサダー
プライシングの事例としては
・Sonyの「FES Watch」によるクラウドファンディング
などをご紹介頂き、各プロジェクトにおいてどのように「コ・クリエーション」が活用されているかをご説明いただきました。
■電通が求められる役割
次に、具体的な業務についてのご説明がありました。
実際に電通が行っていることは、大きく分けて「橋渡し型」「1プレーヤー型」「寄り添い型」の3つのタイプがあるそうです。
「橋渡し型」はWin-Winの関係になるステークホルダーを探して紹介するタイプ、「1プレーヤー型」は消費者の代表として参加するタイプ(例えば若い女性の研究を専門に行う“GAL LABO”が参加する等)、「寄り添い型」はプロジェクト全体の進行役として参加するタイプのもので、ほぼすべてのお客様に興味を持っていただけるそうです。
しかし、最終的に求められるのは「売上志向型」。
「価値の創造」という成果を確実にあげていくためのオペレーションについて、具体的な経験に基づいたいろいろなお話を伺いました。
■事例の紹介
コ・クリエーションの「プロセス」についても、食品会社の新商品開発の事例を通じて具体的にご紹介頂きました。
ITシステムを用いて300のアイデアを集め、メンバーが一同に会するリアルセッションによって3つの案に集約していった18週間のプロジェクトなどが例にあげられ、参加されるステークホルダーの皆様への案内の方法に始まり、ITシステムによるアイデア出しの方法、リアルセッションごとのメンバーの選び方や開催方法などが、事例のゴールや状況に応じてどのようにデザインされるのかを説明して頂きました。
■コ・クリエーション型マーケティングのポイント
上記を踏まえ、コ・クリエーション型マーケティングのポイントが5つにまとめられ、説明されました。
■コ・クリエーションを支えるテクノロジー
引き続き、電通国際情報サービスの金山様より、コ・クリエーションを支えるITサービス「Spigit」のご紹介がありました。
アイデアの数が集まるに従い、アイデアの価値の「平均値」が全体的に下がっていく一方、「分散」が拡大し、「尖った非常に価値が高いアイデア」が出てくるようになるようになるそうです。「良いアイデア」が出てくるようにするための、アイデアを集め、評価し、採用していくプロセスが「Spigit」には実装されており、実際のオペレーションを交えたご説明がありました。
■質疑応答
参加された方々からも、様々なコメントがありました。
・無印での事例などでは意図的にユーザー同士のインタラクションを起こさないようなユーザビリティになっているが(起こしすぎると逆にコモディティ化する傾向があるから)、「Spigit」もそのような機能をもっているか?
→意図的にコミュニケーションがとれないようにするということはしていない。
・多様なアイデアをどう収束させているのか?
→発散と収束の2つのフェーズがあるが、収束の際は「いいね」の数やコンプライアンスの問題やフィージビリティなどの観点から絞っていくが、最初からそれらを取り込むと、いいアイデアが出にくくなるため、最初は広くアイデアを出すようにしている。
・どれくらいの人数・どれくらいのコメントがあると「コ・クリエーション」の成果が出るかというところの「肌感覚」はあるか。
→人数の多さというよりも、「人種の質」かなと思っている。
→「Spigit」での経験では、500名くらい集まってきたあたりから違うレベルのアイデアが出て来ている実感がある
・モデレーターの「仕切り力」が大きく成果に影響すると思うが工夫している点があれば教えてほしい
→B2BとB2Cの場合で異なる印象。
→経験的には2週間で一度熱が冷めてしまうため、2週間で一度閉じてから、再度リアルセッションを作るなどしている。
→事前にセッション参加者に全員会ってどのような場にすればいいか検討したりしている。
→B2Bの場合にはトップマネジメントの方がきちんとコミットしていることを明示するようにしている。
・「意図せざるヒット」につながるファシリテーションやプロセスはあるか。初音ミクのような自発的なコミュニティが生成されるケースもある。
→(参加者コメント)何が流行るのかは全く読めないと思っているので、流行ってきたものをどう活用するかを考えている。
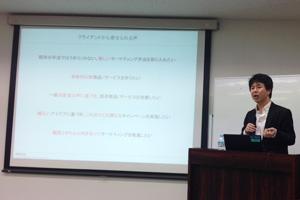
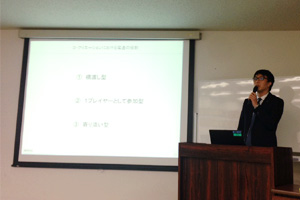
写真左から、講演中の河野氏、濱口氏
【サロンを終えて】
多くの質疑応答のやりとりがあった今回のサロン、終了後の名刺交換や個別のやりとりも活況で、とても「マーケティングサロン」らしい会になりました。
これもゲストのみなさまが作りだした雰囲気と興味深いやりとりのおかげだと思います。
会場に映画関係の方がおりコメントを頂いたからかもしれないですが、コ・クリエーションを進める講師の皆様のお話を映画監督のコメントに似ていると感じました。
この場を借りて、ゲストスピーカーをお引き受けいただきました河野様、濱口様、金山様、ご参加いただきました学会員の皆様に、あらためて心より感謝申し上げます。

集合写真(前列左から4・5・6番目がゲストの河野氏、濱口氏、金山氏)
(サロン委員:高村和久、三谷暢宣)











