|
第14回ユーザー・イノベーション研究報告会レポート「消費者との共創、誰とどのように組むべきか? ― コンテストを通じたアイデアの募集 ―」 |
#いまマーケティングができること
第14回ユーザー・イノベーション研究報告会(春のリサプロ祭り・オンライン) > 研究会の詳細はこちら
テーマ:消費者との共創、誰とどのように組むべきか? ― コンテストを通じたアイデアの募集 ―
- 解題:
青木 慶(甲南大学 マネジメント創造学部 准教授) - 受賞経験者が語る、コンテスト参加の意義
徳田 周太(株式会社 北陸博報堂 マーケティングプランナー)
丸本 瑞葉(株式会社 SciEmo 代表取締役 CEO) - パネルディスカッション:コンテスト実施の意義
德田 周太(同上)
丸本 瑞葉(同上)
西川 英彦(法政大学 経営学部 教授)
青木 慶(同上)
他研究会メンバー - 質疑応答
日 程:2023年3月18日(土)16:30-18:00
場 所:Zoomによるオンライン開催
【報告会レポート】
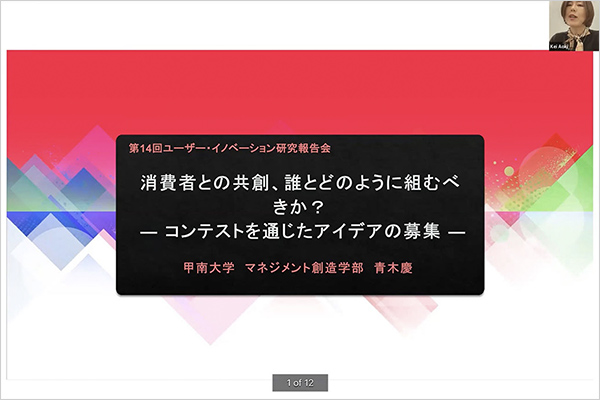 消費者との共創に取り組みたいが、果たしてどのように進めて良いのかがわからない。そんな悩みを抱えるマーケティング担当者は、少なくないのではないか。もし消費者と解決したい課題が明確なら、コンテストという形でアイデアを公募してみてはどうだろう。本セッションでは、こういったコンテストの受賞経験者をゲストに迎え、応募に至るまでの動機や、どのようなバックグラウンドを持ち合わせているのかについて紐解くことを目指した。
消費者との共創に取り組みたいが、果たしてどのように進めて良いのかがわからない。そんな悩みを抱えるマーケティング担当者は、少なくないのではないか。もし消費者と解決したい課題が明確なら、コンテストという形でアイデアを公募してみてはどうだろう。本セッションでは、こういったコンテストの受賞経験者をゲストに迎え、応募に至るまでの動機や、どのようなバックグラウンドを持ち合わせているのかについて紐解くことを目指した。
青木准教授による解題に続き、德田氏によるプレゼン「いち生活者として感じるコンテスト参加の意義」が行われた。学生時代より「ロボコン」や各種のアイデアコンテストに関心があったという同氏だが、学生時代のモチベーションが「客観的な評価がほしい」ということだったものが、現在は「アイデアを世に投じ主体的に新しい価値を生む実験をしたい」と変化したという。同氏は現職においても、そして個人の趣味であるDIYでも、「理想のモノがなければ、あらゆる手段を使って、できる限り自分で作る」という考えのもと、特に技術面での実現可能性を追求するため積極的にコンテストに応募しており、その具体的な事例も紹介された。
最後に、そうした活動を通じて「次の実験・価値創造のための資産(賞金・ロイヤリティ)、「協業パートナー」、そして「知的資産・シーズ」の獲得ができた、と整理されプレゼンが終了した。
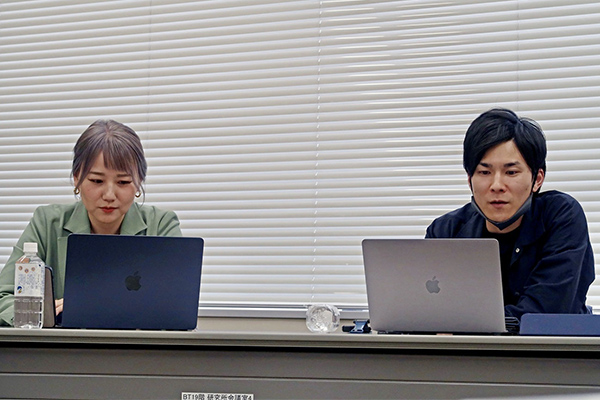
写真左より、丸本氏、徳田氏
続いて、丸本氏のプレゼンが行われた。高校時代に経験した、タイの貧困層向けボランティアで「世界の違和感や歪みをなくすための事業開発」に興味を持つようになり、大学時代にイノベーションマネジメントのゼミに所属し大学生の商品企画コンテスト「Sカレ(Student Innovation College)にも参加した同氏。就職したメーカーで新規事業開発や商品企画などを担当したが、その実践方法に疑問を感じ、休職しMBAコースで新規事業創出方法論を専攻、アクションリサーチの手法で研究を行なった。その過程で、「短期間で自分の企画が評価され、質の確認ができること」からいくつかのビジネスコンテストにも参加するようになり、その経験から「ものづくり人材との人脈形成」と、独自の「メソドロジーの開発」という成果が得られたという。
後者は、コンテストにおいてどういった選考理由で受賞したのかを振り返り、その共通点が「コンセプト/ユーザーインサイトへの共感」だったという点を認識、そこからユーザーのもつ「共感される感情」を起点として新規事業を創出する方法論「Emotion Driven」のことで、その概要も紹介された。最後に、同氏がコンテストに挑戦するモチベーションとして、「アイディアの社会実装と社会への貢献、「メソドロジーの確立と実践」、そしてそもそも「作ること」が好き、という気持ちがベースにあるという考えが示された。

写真左より、丸本氏、徳田氏、青木教授、西川教授
両氏によるプレゼンの後、パネルディスカッションが行われた。まず西川教授から、両氏の違いとして「自らのために」やるのか、「誰かのために」やるのか、という点があるという見解が示された。ユーザー・イノベーターの研究では、主に前者のようなユーザーを想定してきており、丸本氏のような後者タイプの存在があるということはとても興味深い、という指摘であった。
続いて青木准教授から、応募する際にジャンルや主催企業にはこだわりがあるか、という質問が示された。ユーザー・イノベーションを活用したい企業にとって、この点は示唆をもたらす。両氏とも「こだわりは特にない」という回答だったが、德田は当該企業の「ものづくりへの姿勢や、どのような思いでコンテストを開催しているのか、に共感できるかどうか。」を重視しているとの考えが示され、丸本氏からは「社会実装するために内部の体制をどこまで整えているか、アイデアを得てその後それが活用されずに終わることにならないか」ということを注視しているという考えが示された。
最後に、オンライン参加者からも多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答で研究会が締めくくられた。
(文責:清水 信年)












